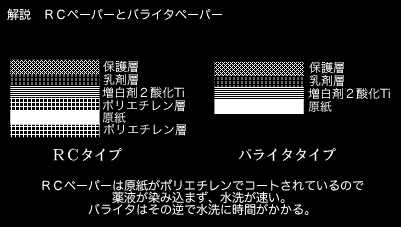
写真部に入り、その部室を見回して最も興味をそそるのはやはり引き伸ばし機を始めとした暗室機材だろう。何やら先輩がオレンジ色の光の下でピンセットを使ってバットをかき回していたり、変な黒いタンクを裾の塞がったジャンパーのような袋に入れていたりと、何となく暗室に興味を引かれて写真部に入った皆さんも多いであろう。全く好きでもなければ昼間っからあんな臭くて暗いところで作業していられないはず。もともと俺が何故この冊子を著そうかと恩ったかというと、高校写真展や文化祭などで見る写真の処理が余りにも適当で乱雑であったからなのだ。見るからにして指定液温や処理時間を守っていなかったり、コントラストが余りにも高い/低い、またゴミだらけ一写真で表現するという問題以前に「正確な処理」という前提条件をクリアしていない写真を多く見受けたからなのだ。しまいには写真の内容以前に仕上げの善し悪しで入賞を決めているような写真展もあったりして、暗室フリークの俺としては涙も出ない。写真とは化学に依存する表現である。表現行為であると同時に半分は化学反応の賜物なのだ。フィルムを詰め、撮影するとフィルムの銀粒子上には潜像(latent image)という目には見えない像が出来ている。この潜像が遠元作用を持つ現像液によって目に見える銀粒子の画像となるのだが、しかしこのままだとフィルムには感光性が残されたままで、光に当てると真っ黒になってしまうので定着という工程を経なければならない。これは画像の中でも光のあまり当たっていない(黒っぽい)部分、即ち黒化していない、感光性のある銀をハイポ(チオ硫酸ナトリウム、水槽に入れる水道水を中和する例のヤツ)に溶かし込んでしまって感光性を失わせようというものである。これでようやく写真はネガの形となって日の目を見ることになるのだ。この一連の工程は純粋な化学反応であり、規定の時間や温度を守らないと正しいネガは望めないのだ。これは言語で言う文法のようなものであり、この文法に従わない写真は観賞に耐えない。写真歴の長い皆さんも、そうでない皆さんも、もう一度この厳粛な事実に立ち返ってきちんとした処理をマスターして欲しい。ちょっと説教臭くなってしまって申し訳ないが、これも今まで撮影について言ってきたように、場数を踏めば踏むほど上達する。暗室の独特な雰囲気一あの匂い、あの密室で育む友情、あの何でもありな、学校の中にありながらどこよりも自由な治外法権性を楽しみながら、素晴らしい暗室マスターになって欲しい。さてその暗室の中で行う作業は?フィルム現像?プリントの2つに大別できる。それではそれらについて順番に解説していこう。
先ほどにも少し述べたが、フィルム現像とはフィルム上の潜像を黒化銀に還元する行為である。まあ要するに、黒白のネガを作ることだ。まず、用意するものは、
1.現像タンク
プラスチック製のものとステンレス製のものがある。ステンレス製のほうが耐久性に富むが、初心者には取扱いやすいプラスチック製が良いと思う。特に俺が御勧めしたいのはキング/パターソンのタンクで、フィルムが装填しやすく薬液の出し入れもスムーズ。
2.現像リール
現像タンク指定のものを使うこと。片溝式、両溝式、ベルト式の3つの種類があるが、初心者には片溝式やペルト式の物が使いやすい。
3.ダークバッグ
裾の塞がったジャンバーのような袋で、この中でフィルムをタンクに装填する。予算の許すかぎり大きなものを買ったほうがよい。
4.フィルムピッカー
巻き込まれたフィルムの先端を出すための道具。
5.液温計
現像液や定着液などの温度を測るのに使用。
6.かくはん棒
現像液や定着液などを調製する時に必要。
7.メスカップ
目盛りのついたカップで、これまた現像液や定着液などを調製する時に必要。
8.薬液貯蔵用プラスチックタンク
作った薬液を保存するのに使用。
9.フィルムクリップ
処理済みのフィルムを乾燥させるとき、紐に吊り下げるために使用。
10.写真用スポンジ
処理済みのフィルムを乾燥させるとき、水滴を拭うのに使用。
この他に、乾燥済みのフィルムを収納するネガシート、ハサミ、現像時間を計るための時計(写真用に暗室時計というのもあり、そちらの方が便利)も欠かせない。また、必要な薬品類としては、
現像液、定着液、酢酸、水洗促進剤(QWが安価で便利〉、水滴ムラ防止剤(フジドライウェル)があげられる。それでは各手順の説明。
a.フィルムピッカーでフィルムのベロを出す。
フィルムピッカーの説明書に従う。初めはコツをつかめずに苦戦するが慣れれば早い。また、フィルムピッカーが無いときには既にベロが出ているフィルムの先端を舌でなめて濡らし、それを出ていないほうのフィルムに差し込んでそれが引っ張り込まれる感じがするまで出ていないほうの軸を回す。それから差し込んだフィルムを引き出せば、つられてベロが出てくる。ダークバッグの中でパトローネ(フィルムが入っている缶をこう呼ぶ)を栓抜きで開けるのもよいが、フィルムピッカーを使う方が良い。
b.ダークバッグの中でフィルムをリールに巻き付ける。
ここが初心者には最も難しいところだ。経験者に教わるのが最も確かなのであるが、ここではプラスチック片溝式の場含について解説する。まず、ベロを出したフィルムの先端をリールの軸の金貝の下に潜り込ませて固定する。次に、パトローネを右手に持ち、リールだけを動かす感じで溝に入れて行く。徐々に巻き込んでいってフィルムが終わりの所まで来たらそのフィルムの終端部を左手でつまみ、右手のパトローネをフィルムの短辺に対して角度を付けて引っ張ってもぎ取る。そしてそのリールを中軸に差し込み、タンクに入れてフタをすればよい。勿論ダークバッグにこの一式を入れ、プィルムに光が当たらないようにしなければならない8たまに明るいところで目をつぶってやってしまう人もいるが笑えない。まあここに書いてあるだけでは分かりにくいので、経験者や専門書を参考にして欲しい。
c.現像液をタンクに入れる。
時計を用意して時間を計れるようにしてから現像タンクにタンク指定の量の現像液を入れる。この際、現像減の温度は適正になっているようにすること。(一般的には20℃)現像液の温度を調節するためには、温度を上げたいときには湯を入れたバケツに貯蔵タンクを入れればよいし、温度を下げたいときにはビニール袋に水水を入れたものを用意し、それを現像液を入れたメスカップに浸せばよい。とにかく20℃を死守するべく工夫されたい。そのためにも暗室に冷蔵庫と電気ポットは必需品だ。
d.現像時間を計りつつ攪拌する。
タンクに現像液が入り切ってから抜け切るまでの時間のことを現像時間と呼ぶ。現像液が入り切ったと同時に時間を計り始め、最初の30秒間は連続してかくはんする。かくはんの方法はタンクによって倒立してかくはんするもの、中の軸を回してかくはんするものと様々だが、各々のタンクの説明書に従う。その初期かくはんが終わったら、次にタンク内の気泡を取るためにタンクを叩く。タンクを10センチ程度の高さから流しや床に叩き付けるのである。この際に余り強く叩いても効果がないばかりか、プラスチックタンクの場合破損する恐れもあるのでその辺は適度に。そして後のかくはんは1分間ごとに10秒、規則正しく行う。
e.現像液を排出する。
現像時間終了が近づいたら、ちょうどその時間に液が排出し終わるようにタンクを傾けて排出する。液を再使用する際は貯蔵タンクに戻す。ここまでが現像の工程である。
f.停止浴を行う。
現像液を排出し終わったらすぐに停止液を入れる。停止液の作り方であるが、50%酢酸を水1lあたり30ml入れたものが停止液となる.20〜30秒間連続かくはんしてから液を排出する。以後、各処理の時間は現像時間と同様に計る。尚、停止液の温度は15〜25℃に保つこと。
g.定着処理をする。
次に定着液を入れる。この処理の際も現像と同様に始め連続かくはん30秒、後には1分間ごとに10秒のかくはんを行う。定着液の液温は現像液ほどどシビアではないが、20〜25度に保ちたい。しかし、絶対に20℃以下にならないように調節すること。定着不足の原因となり、後日ネガが変色する原因になる。また、繰り返し利用が可能だからといって余り酷使しないこと。特に夏季は保存性が悪くなるため、3週間以上経った液は取り替えること。定着時間は説明書を参照。
h.水洗をする。
ただ単に流水で行うだけでもよいのだが、ここでは水洗促進剤を用いたいところだ。大幅な水洗時間の短縮が可能になる。まずは30秒間予備水洗を行うが、この際現像タンクのフタは外しておくこと。それが終わったら水洗促進剤に1分間浸す。その後再ぴ流水で5分間水洗する。尚この際に水がタンクの底の方まで水が循環するようにホースを使うとよい。メスカップにリールを移し替え、その底にホースを差し込めば完全だ。水洗が不足してもネガの変色の原因になるので気を付けたい。
i.水滴ムラ防止処理をする。
水洗が終わったリールを水滴ムラ防止剤に浸す。この時間は30秒間。この薬品は界面活性剤で、水を切る効果がある。
j.乾燥する。
全ての工程が終わったフィルムはフィルムクリップで挟み、吊り下げてから水滴ムラ防止剤を含ませて絞った写真用スポンジで拭って乾燥させる。この際にホコリの多い場所は縮対に死んでも避けること。ネガにゴミが付き、プリント上に白い痕跡(スポットという)が残って見苦しい。乾燥したら6コマごとにハサミで切ってネガシートに入れる。とまあ、文章で読んだだけでは分かりにくいであろうがここまでが現像の工程である。無責任ではあるが、皆さんの身近によい先輩・顧間がいることを願ってやまない。暗室作業のみならず様々な意味での先輩が。
では次に、各工程に用いる薬品について少し。
1.現像液
YドバシカメラやBィックカメラに行くと余りにも多種の薬品類に圧倒されるが、自分の基本となる現像液は1種と定めてそれを使い続けたほうがデータが揃って安定する。しかし何故、あんなにも多くの現像液が市販されているのだろうか。それは基本的な性能や処方ははとんど変わらないのに、各フィルムメーカーが自社プランドの現像液を出そうとするからである。かと言ってそれらに全く個性がないかと言えばそうではなく、それぞれのネガづくりに応じた現像液のタイプがある。ではそれぞれのタイプについて検討してみたい。
a・微粒子現像液
ごく一般的な現像液で、「微粒子」という呼ぴ方をされているが何も特別な意味はない。現像液の研究が進んでいた当時の最先端の名残なのだ。全てのフィルムの現像に適しており、すべての現像液の基準と言える。標準的なコントラスト、濃度、感度が得られる使いやすいものだ。コダックD-76,富士フジドール、イルフォードID-11などがこのタイプである。
b・超微粒子現像液
aよりも高画質が得られるような処方の現像液。主にISO100以下のフィルムに相性が良いが、勿論400のフィルムにも効果はある。コントラストがやや控え目に仕上がり、また現像作用が弱いために撮影時の露出をオーバー目に掛けたほうがよい。即ち実際の感度がわずかに落ちるということだ。ISO400なら320に、ISO100なら80位に設定して撮影すれば良いだろう。コダックマイクロドールX、富士ミクロファイン、イルフォードパーセプトールがこの類。次の項で述べる増感には御勧め出来ないので注意。
c・増感用現像液
実は、フィルムの感度を現像で上げるという裏技がある。例えばIS0400のフィルムをISO1600で撮影し、普通に現像するとネガは薄くなってしまうが、現像の段階でこの種の現像液で処理すれば通常の濃度をもったネガができる。これを『増感処理』と呼ぶ。すなわちフィルムの実際の感度は上昇したことになる。この専用現像液を使わなくても、D76などの微粒子現像液を遣って現像時間を延長すれば同じ効果が得られるのだが、その場含どうしてもネガのコントラストや粒状性(=粒子の細かさ)は悪化してしまうのでこのタイプの現像液が考案された。つまり強力な現像作用とコントラストの上昇を抑える処方になっているわけだ。ところでこの増感処理はISO400以上のフィルムと相性が良い。ISO100のフィルムでは大してこの効果を得られないので注意。せいぜいISO100が200になる程度だろう。増感では通常の処理よりも画質はかなり落ちるので、その辺を覚悟されたい。富士パンドールなどがこの類。
一とまあ大体のところを述べてみた。このほかにも特殊用途の現像液(高鮮鋭性現像液、低温・高温現像液、白黒反転現像液、一浴現像定着液など)があるが、まずほとんど市販されていないし、プロの写真家にも使ったことのない人が多いくらいなのでここでは割愛する。
俺としては初めはaの微粒子現像液から入るのがよいと思う。あらゆるフィルムに対応できるし、現像所もプロ写真家も現像液といえばD76しかないというくらいだからだ。各フィルムの現像時間を後に掲載するので参考にされたい。
2.停止液
これに関しては停止液と銘打って市販されているものは少なく、殆どの場含自分で酢酸を水で薄めて使うことになる。一般的には90%酢酸を水1リットルあたり13ミリリットル加えたものを使う。(50%酢酸の場含はこの倍の量を入れる)もちろん停止液として市販されているものもあり、コダックインジケーターストップバス、中外エルオレンジがその類である。これらの液には疲労によって色が変化する特性を持たせてあり、交換時期が簡単に分かって便利ではあるが、割高。やはり普通の酢酸がよろしいようで。
3.定着液
感光していない、まだ感光性のあるハロゲン化銀を溶解して写真を白日の下にさらせる(=定着作用)ようにするための薬品である。その作用のスピードによって2種類に区分できる。
(1)酸性硬膜定着液
まあ「酸性」は何となく分かるけど、「硬膜」って何?では説明しよう。フィルムには銀が塗布してあることは何度も述べたが、まさか銀が直接塗ってあるはずもなく、ゼラチンを溶かした中に銀粒子を散らしたものが塗ってあるのだ。そのゼラチンは皆さんのご想像通り水分によって軟化する。軟化するとどうなるかと言えばその後の取り扱いの際に傷が着きやすくなったり、ひどい場含には水洗過程で流れ去ってしまったりするから穏やかでない。そこで定着液には「硬膜剤」という物を配合してゼラチンの「膜」を「硬」くしているという次第だ。硬膜定着剤の欠点として、含まれていないものよりも処理時間、水洗時間が長くなってしまうということがあげられるが、この場合そのリスクをカバーするメリットがある。もちろん硬膜剤を含まない定着液も市販されていて、ナニワパンフィックスS、イルフォードハイパムフィクサーなどがその類だが、これらは印画紙の定着に向いていると言える。フィルム用には硬膜定着液がおススめだ。さて前置きが長くなってしまったが、これが一般的な定着液である。どんな種類のフィルムにも適用できる.ただし、コダックTMAXやイルフォードデルタに使用する場合には定着時間を説明書に指示された時間の2倍にしなければならない。これらのフィルムは銀を特に多く含んでいるためだ。富士フジフィックス、コダックフィクサーなどがこの類である。
(2)迅速酸性硬膜定着液
(1)よりも速い時間で処理できるのでこもらのほうがお勧めだが、やや割高。強カな定着作用のためにあまりボーッとして何十分も潰けておくと画像自体が溶解されて薄くなる恐れがあるので注意。TMAX、デルタに対する注意は(1)と同様。富士スーパーフジフィックス、コダックラピッドフィクサーなどがこの類である。
4.水洗促進剤
定着液にはチオ硫酸ナトリウム(ハイポ)やチオ硫酸アンモニウムが含まれており、これらが定着作用の主役を担っているのであるが、これが処理後にも残っているとこれらが硫黄に変化して画像を汚染するために行うのが水洗である。もちろん水洗だけに水を流しておくだけで平気なのであるが、水洗促進剤にはそれらの薬品を中和する作用があり、水洗時間の短縮やより完全な水洗に役立つ。安いものなので必ず使うべきだ。特に冬季、水温が低い場合には水洗作用が落ちるのでその際にも欠かせない。富士QW、コダックハイポクリアリングエージェント、イルフォードウオッシュエイドなどがこの類である。
5.水切り剤
フィルムを乾燥させる際、水滴が乗ったまま乾いてしまうとその跡が残り、プリントに出てしまうのだが、これはそれを防ぐための薬品である。代表的な製品「富士ドライウエル」の説明書には「…30秒間浸してから、ぬぐわずにそのまま乾燥してください」とあるがこれはどうも怪しく、写真用スポンジで拭ったほうが遥かに早く乾燥できb結果も良好である。富士ドライウエル、コニカダックスなどがこの類である。
まあ大体全ての薬品をこうして網羅してきたわけだが、何も難しいことはない。ここにあげたものの中からそれぞれ一つ、自分はこれを使い続けるぞ、というものを定めて、あとは経験するべし。しかし何を使ったらよいか全く分からない、見当もつかないという皆さんのために、俺が個人的に使っている条件を書いてみたい。
突然文字まで大きくしてみたが、これから書くことは絶対に死んでも守らねばならない事柄だ。
以上7条、遵守せざるものは東京湾にコンクリートのベベ着せて沈める。まあこうは書いてもなかなか初めはうまく行かないものなのだ、実際のところ。特に高校写真部の部室においては液温の管理が最大の問題であろう。夏場の水道の水温は平気で24℃位にはなるし、また冬場には15℃を切ったりもする。余談だが昔、さる高校の暗室で酢酸が凍ったことがあるらしい一それはさておき、この問題を解決する最良の方法は暗室に電気ポットと冷蔵庫を置くことである。予算の都合が難しい面もあるとは思うが、まあぴとつここは綺麗な仕上がりを「買う」気分で顧問の皆さんには前向きに検討していただきたい。そのためにも部員諸君は冷蔵庫にジュースを入れたいなどとは口が裂けても言わないように。それが無理なら、職員室や給湯室にもらいに行くことだ。
その液温の上昇/低下の方法であるが、一般的には大きなバケツを用意し、その中に湯や氷水を入れてさらにその中に現像タンクや貯蔵タンクを入れる方法が取られる。また、さらに急いでいるときには湯や氷水をビニール袋に入れ、それを直接温調したい液の中に直接入れると効果的だ。この際、ビニール袋に漏れがないか点検してから使うこと。
また、現像工程においての停止浴は省略することもできる。本来余りお勧めできないのであるが、フィルム現像液のアルカリ度はさほど高くないので時にはこういった処理をする人もいる。この場合、定着液の寿命は短くなるので頻繁に交換すること。
そして現像がいくら素晴らしい結果になっても乾燥の段階で台無しにすることも多い。高校写真展でもっとも良く見られる汚いプリントの原因の多くはフィルム乾燥の際についたホコリがプリント上にでてしまう「スポット」である。あまり人通りの多い場所や掃除の頻繁にされていない場所で乾燥を行うのは絶対に避けなければならない。また、乾燥が終わってネガシートに入れたフィルムも丁寧に扱うこと。時に机の上や引伸し機の周りに裸のままネガを置きっ放しにする人を見かけるが、世が世ならたたっ斬ってやりたいところだ。ふだんは潔癖でない人も暗室に入ったら潔癖症を気取りたい。
まあたらたらと書いてきたが、何よりも経験者に教わるのが早いのであって、何とも無責任な言い方になるがこの文章はあくまで参考にしか過ぎないのである。独力で学びたいのならどんどん様々な条件に挑戦して失敗とデータを蓄積すること。俺が言えるのはそれだけだ。
次はいよいよ作成したネガを印画紙に焼きつける工程である。暗室作業のハイライトとも言えるもので、これに憧れて写真部に入った皆さんも多いであろう。まず、用意するものは、
1.引伸し機
なるべくしっかりしたものを選ぴたい。支柱がヤワなものを選ぶと引伸しプレの原因になる。まあ大体の皆さんが部室にあるものを使うと思うので選択の余地はないのだが、自分で買うのなら富士のFD690やLPLの7700などを選ぴたいところだ。とにかく、引伸し機は大きければ大きいもののほうがよい。極端に安いものは買わないほうがよい。
2.引伸しレンズ
これも極端に安いものは避け、フジノンやニッコール、余裕があればローデンシュトックのロダゴンレンズを使いたいところだ。35ミリサイズのネガの引伸しには50ミリのレンズを使用する。
3.引伸しタィマー
引伸しのときの露光時間を制御するタイマー。これがなくても時計を見ながらON/OFFすればよいだけの話なのではあるが、均一な結果を求めるためには欠かせない。
4.フォーカススコープ
引伸し時のピントを含わせるのに用いる。様々な方式の物があるが、ピークのものが使いやすい。
5.イーゼルマスク
印画紙を固定するために使うマスク。4切用のものを用意すればよいだろう。
6.セーフライト
暗室の赤い光、それがセーフライトである。印画紙は普通の太陽光や螢光灯にあてると駄目になってしまうが、この赤い光は印画紙の感じる光の波長をキャンセルしたものであるので安全で、(ゆえに”セーフ”ライトと呼ぶ)作業時に使われる。なおいくら安全だからといって当て過ぎは禁物で、なるべく印画紙は素早く処理し、不要に長い時間セーフライトにさらすことのないように。一般的には20Wの白熱電球を専用のランプハウスに入れ、その前にセーフライトグラスという赤いフィル夕ーをかけたものを使う。このグラスは各印画紙に対応したものを使うこと。すでに暗室にあるものを使うことが多いと思うが後述の「多階調印画紙」を用いる場含には専用のものを使わないと「カプリ」(=印画紙が光に当って黒っぽくなったりコントラストが低下したりすること)を生じる。
7.バット
印画紙を現像処理するために使う。余裕をもって大きなサイズのものを使いたい。これも4切用を用意すればよいだろう。現像、停止、定着、水洗用と少なくとも4枚は必要である。
8.竹ピンセット
いわゆる「竹ピン」である。現像、停止、定着の各工程に一本ずつ必要。まあ普通は3本セットで売られているのでそれを求めればよい。
この他に、現像でも使ったメスカップ、薬品貯蔵用ポリタンク、液温計、攪拌棒や、焼き込み/覆い焼き(後述)に使う厚紙や針金、余裕があれば印画紙乾燥機あるいはへアドライヤ、プロアプラシ(絶対に必要!)、フィルムクリーナーも欠かせない。まだ何か書き忘れているような気もするがそのつど書くことにする。
また、必要な薬品類は、1.印画紙用現像液、2.酢酸、3.定着液(フィルムと同じ物を求めればよい。但し、兼用はしないこと)である。では、手順を説明しよう。と、その前に印画紙の2つのタイプについて解説しなければならない。それによって各処理の時間が違ってくるからだ。印画紙には「RCタイプ」と「バライタタイプ」の2つの種類がある。(下図)
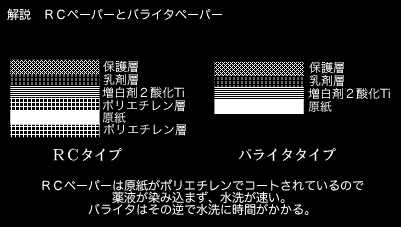
図のとおり、RCはボリエチレンで原紙がコートされており、またバライタでは原紙はむき出しのままになっている。これらの要素が処理上どのような影響を与えるかと言えば、バライタの方は薬品が紙の繊維の中にまで染み込んでしまうために水洗の効率が非常に悪い。RCではその逆で水洗は5分程度で済んでしまう。しかし、これではバライタペーパーの存在意義が無いではないか、と思われるかもしれないが、それは誤りだ。たしかにRCは迅速処理を目的として開発されただけあって非常に便利なのではあるが、なにしろ紙がポリエチレンでコートされているために質感が安っぽく、テカテカ光って黒がきちんと締まって見えないのである。このため展示用のプリントはほとんどバライタで作られているし、プロ写真家の中にはバライ夕しか認めない人もいる。だがそれにしてもバライタの処理は面倒だ。よってこれは余裕ができたら使うことにして、まずはRCペーパーの処理を解説したい。RCでもきちんと焼けば見られるプリントができるのだ。
a.薬品を用意し、バットに入れる。
印画紙用現像液、停止液、定着液を用意し、それぞれをバットに入れる。4切用のバットなら2Lが適量だ。尚、停止液は酢酸を水にフィルム現像の項で解説した要領で溶解したものを使う。それぞれの液は20℃に保つこと。多少上昇してもよいが、20℃以下になるのは絶対に避けねばならない。液温を調節するのもフィルム現像の項で解説した方法で行うが、ここではぬるま湯あるいは氷水を入れたバットを処理液のバットの下に敷く方法が簡単でよい。水洗用のバットには水を適当に入れておく。これらのバットは各処理用として区分することが望ましい。(現像用、停止用一と書いておき、他の処理には使わない)
b.プリントしたいネガを選んでネガキャリアに入れる。
引伸し機のへッドの部分にネガを挟むためのパーツがあるが、それを取り外してネガのプリントしたいコマをその窓に合わせて挟み込む。
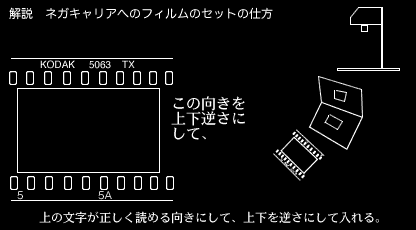
この向きを間違えると左右逆な写真になってしまうので慣れるまでは注意が必要だ。(これを「裏焼き」という)ネガを挟み込んだら、プロアでネガに付いた埃を払う。それでも取れない埃がある場合にはフィルムクリーナー(富士から発売。茶色の小瓶に入った液体で、これを脱脂綿や木綿のハンカチなどに染み込ませてゴミ・埃を拭き取る)を使う。それでもだめならネガをドライウェルで洗ってもう一度乾燥させる。
c.引伸しレンズを取り付け、イーゼルマスクのサイズを合わせる。
しばしば引伸し機にレンズが取りつけっぱなしになっている例を聞くが、これは絶対に避けなければならない。湿気の多い暗室に、誰が自分のカメラのレンズを放置しようと思うだろうか。それと同じく引伸しレンズも作業が終わるごとに所定のケースにしまわなければならない。さて、引伸しレンズのマウントは万国共通のネジ込み式になっているので取りつけは簡単である。ネジ込んで止まるところまで回せばよいのだ。そして次に、イーゼルマスクの羽根を自分が引き伸ばしたい写真のサイズに合わせる。印画紙の袋にその寸法は書いてあるのでそれに合わせればよいのだが、一般的にはその寸法から長辺・短辺ともその長さから1センチ引いた長さを合わせること。こうすることで、各辺5ミリのフチを持ったプリントが作れるのだ。これはそれぞれのイーゼルによってまちまちなので、説明書を読むか試行錯誤して欲しい。
d.画像のサイズを合わせ、ピントを合わせる。
ここから先の工程はセーフライトの下で行うこと。もちろん明るいところでセーフライトを使うという意味ではなく、部屋を暗室にした上でセーフライトの光のみで作業を進めるのだ。さて、ここで引伸しタイマーの"FOCUS"というスイッチを押すと引伸し機のランプが点灯して先ほど挿入したネガの画像がイーゼルの上に投影される。そして引伸し機のヘッドを上下に勤かし、かつピント調整ノプを回してイーゼルに合わせたサイズの画像を得るのである。書いてあるだけでは本当に分かりにくいのは勘弁していただきたい。まあやってみることである。大体のサイズとピントが決まったら、次にフォーカススコープを使って厳密なピント合わせを行う。フォーカススコープもこれまた実際に使ってみないと使いこなしにくい代物なのだが、まずこれを投影された像の中心に置き、覗いてみる。そして同時にピント調節ノプを回転してゆくと、一瞬何かザラザラした絵柄が見えてくるのだが、これはフィルムの粒子であり、この一つ一つの粒子がもっともハッキリ見える位置でピントが合ったことになる。この際の引伸しレンズの絞りは開放にしておくこと。その粒子を確認したら、次にレンズの絞りを5.6まで絞り、もう一度、こんどは画像の4隅のピントを確認する。これで全面にピントが来る場合が殆どであるが、もし合っていない場合には絞りを8や11まで絞っそみる。それでも駄目な場合には引伸しヘッドとイーゼルの平行が狂っている恐れがあるので調整されたい。引伸し機の説明書を参照のこと。
e.試し焼きをする。
ピント合わせが済んだら、もう一度"FOCUS"ボタンを押してランプを消す。次に適当な大きさの短冊状に印画紙を切り、段階露光を行う。
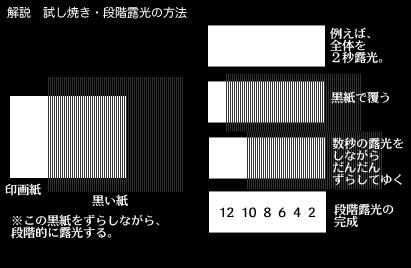
もっとも俺などは印画紙を適当な大きさにちぎって適当な秒数で一発で焼いているのでこう書いていると白々しい気分になってくるのだが、何事も初心が大切、しっかりやって欲しい。後のことは知らん。印画紙の露光も撮影時と同じく時間を倍・倍にして行くと分かり易い。また引伸しレンズの絞りも1段絞り/開けるごとに光の量はl/2/2倍になる。しかし引伸しの場合はネガに対して十分な被写界深度を与えないとシャープな写真にならないので、この絞りは4以下にしないこと。
ちなみに印画紙には裏と表があるので注意しなければならない。セーフライトに反射させてみて良く光るほうが表である。この表を表にすること。裏にしてしまうとボンヤリとしか絵が出ないので焦る。まあ一般的なネガに対してはこの試し焼きの秒数は絞りF5.6で4秒・8秒・16秒・32秒位から始めてみようか。勿諭これで決まりというところはないので大体で良い。秒数を倍倍にしてゆくのがミソ。
f.現像処理する。
さて、ここまできたらいよいよその印画紙を現像してみる。初めに用意した現像液に印画紙を裏返しにして浮かし、(滑り込ませるほうが良いか一)そして竹ピンセットを使ってすぐに表に返し、90秒間攪拌する。この時に印画紙に傷を付けたり、折り目を付けないこと。また絵が濃くなってしまったからといって、時間半ばで上げないこと。観念して90秒間を過ごすべし。濃すぎるな、と思っても明るいところで見るとそうでもない場合が多い。その違いが分かるようになれば君ももう暗室マスターだ。それが済んだら後は同様に停止20秒、定着約3分(定着液の説明書参照)に順次移してゆく。この時、竹ピンセットは各処理液の専用とし、混用は避けること。特に停止液・定着液に使ったピンセットを現像液に入れてはならない。印画上に茶色の汚染を生じる原因となり、また現像液の寿命を縮めてしまう。それが済んだら、いよいよ室内灯をつけて画像の確認に移る。この時、印画紙の袋は死んでも開じておくこと。ベテランでも忘れることがある。
g.印画の調子を見る。
さて、非常に難しい項目となった。どんな濃度の写真が良いかという問題はひとえに個人の主観にかかっている問題だからだ。しかし、高校写真展や、他の人が焼いたプリントで何となく「これは良くないプリントなのではないか」と感じたことは誰にもあると思う。その原因は様々であろう。濃度が高すぎる/低すぎる、コントラストが高すぎる/低すぎる、ゴミが写っている、などなど。一般的に良いプリントとは、・適度なコントラストをもち、・真っ白なものもわずかにトーンを持ち(印画紙の地の白は出さない)、・黒い部分は不必要に黒くなくかつ印画紙の最大濃度を生かし、・スポット(前述)が見られない物をさすのだと思うが、実際に物が黒白で見えない以上は究極の黒白の調子再現というのは有り得ないと思う。まずは、様々な濃度のプリントを作り、また写真展を多く見ることによって審美眼を磨いて欲しい。また、新聞程度の印刷の黒白写真を参考にするのは避けたい。あれはコントラストが高すぎる。
h.本焼きする。
試し焼きによってここだ、という秒数が見つかったら次は実際の印画紙でプリントする。印画紙の表裏に注意してイーゼルマスクにセットし.引伸しタイマーにその秒数をセットして露光をスタートする。普通のイーゼルマスクなら印画紙の左上隅をきちんと合わせて挿入すれば良い。この間に引伸し機を振勤させないようにすること(引伸しブレの原因となる)。露光が終わったら試し焼きと固じように現像処理してめでたくプリントの完成となる。
i.水洗する。
RC印画紙の場合の水洗は非常に迅速に済む。定着が終わったプリントを水洗用バットに入れ、流水で約5分間水洗する。これを撹拝しながら行うとさらに良い。また、次々にプリントを作ってゆく場合、水洗バットにもどんどんプリントが溜まってゆくものだが、この場合の水洗時間は最後にプリントが入ってからの時間を基準にすること。水を流しっぱなしにしているから良いではないか、と言われるかもしれないがこの場合だとどんどん水洗水中に定着液が混入してしまうために水洗効果がないのである。バットの上から水を掛けるのではなく、ホースを使ってバット中に新鮮な水が行き渡るようにも心がけなければならない。
また、より完全な水洗を目指したい同きには「カスケード水洗」という方法もある。
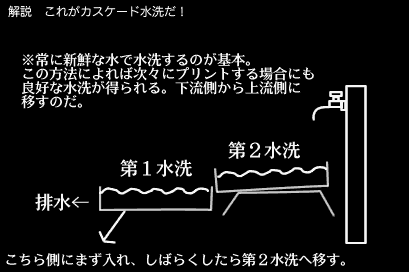
j.乾燥する。
乾燥が速いのもRCの魅力であり、写真用スポンジで表面の水滴を拭って洗濯ばさみで吊しておけば20分程度で乾燥できる。急いでいるときにはへアドライヤも利用できるが、専用の乾燥機があれば尚良い。
以上、プリントの手順を概略的に解説してきた。もちろんこれだけ知っていれば十分なのだが、より完全なプリントを得るための知識をこれから書いてみたい。
印画紙の箱に「フジプロFM2」「GEKKOSUPER SP VR2」などと書いてあるが、その最後につけられた「2」や「3」などという数字を印画紙の「号数」と言う。これは印画紙の持っているコントラストを表す数字で、これが大きければ大きいほどコントラストは高くなる。ちなみにプリントのコントラストが低い状態を「硬い」、その逆を「眠い」というので覚えておいて欲しい。(表を参照のこと)
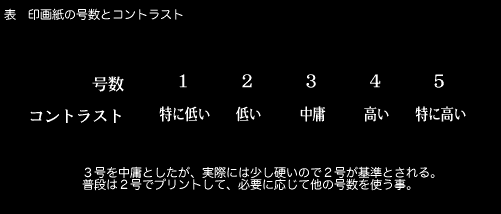
初めにどんな印画紙を買うべきか書かなかったのだが、まずはRCペーパーの2号紙を買うこと。商品としては富士の「フジブロWPFM2」や、三菱製紙の「GEKKOSUPERSPVR2」などがあるので好みに応じて選ぶように。サイズはカビネか6切がちょうど良いであろう。また、「光沢」という種類の物を買ったはうが見映えはする。「半光沢」「無光沢」というのもあるが、皆結局光沢に帰って行くのである。コンテストに応募する際も光沢を使ったほうがよい。ところで、何故このように多種の号数をもった印画紙があるのだろうか。それは、様々なコントラストをもったネガに対応するためである。即ち、濃度の低い、コントラストの低いネガに対しては号数の高い印画紙を使い、逆に対しては号数の低い印画紙を使えばそれぞれ中庸のコントラストをもったプリントを得ることが出来るのだ。実はフィルム現像のところで書くはずだったのだが、ネガには適正な濃度というものがある。専門的には「デンシトメーター(DencityとMeterの造語)」というもので計測するのだが、一般的にはそんなことは誰もしていないので目見当で判断することになる。大体露出のミスがなく、現像も適正な温度と時間で出来ていれば適正なネガが出来るのであるが、時には露出ミスや現像ミスで濃いネガや薄いネガを作ってしまうこともある。ちなみにネガを新聞紙に乗せてみて濃度の一番濃い部分で文字がわずかに読める程度の濃度をもったネガカが適正なネガであるといわれているのであるが、これも経験によって体得するしかない。まず自分の焼きやすいネガを、しかも2号の印画紙で焼きやすいネガを作ることだ。その為には指定された現像時間を変更する必要があるかもしれない。とくにコダック社指定の現像時間では濃く上がりがちだ。
とりあえず、薄いネガになっちゃったなという時は4号や5号、濃くなったときには1号や2号を使えばよいのだとぴとまずは覚えておいて欲しい。だが、そのために1号から5号までの印画紙を常に揃えておくのは金も掛かるし場所も取る。そのために便利なのが「多階調印画紙」だ。これは引伸しレンズの前に号数を変換させるフィルターを掛けると1種類の印画紙が1号〜5号に変化する大変便利なものである。フィルターが別売で四千円ほどするのが少々痛いが、揃えておいて損はない代物だ。この印画紙も普通の印画紙と全く同じように処理できる。こんなものに頼らなくても常に綺麗なネガが作れればもっとも良いのだが一俺も愛用している。是非お勧めしたい。製品としてはGEKKOMULTI、ILFORDMGIV、富上バリグレードWPなどがある。この3種についてはフィルターも共用できて便利だ。コダックのポリマックス2というのもあるが、これは全く専用のフィルターにしか対応していないのでお好きな方はどうぞ。
例えば曇り空を入れ込んだ写真で、空が真っ白になってしまう。また陰の部分をもう少し出したい時。そこが焼き込み/覆い焼きの出番である。単純に考えれば分かることだが、白い場合は露光を増せばよいのだし、逆は減らせばよいのだ。これを画面の特定の部分に掛けることを焼き込み/覆い焼きという。具体的には下図のような道具を自作して行う。
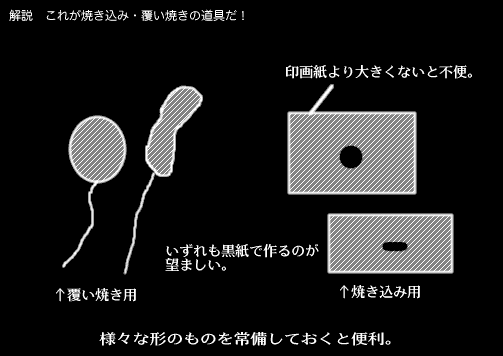
この穴や円盤を利用して部分的な露光の量を調整するのだが、実際これを行って初めて作品と呼べるプリントになるのであるから侮れない。コツがひとつあって、それはこれらの道具を1ケ所でじっとさせずに小刻みに振動させること。さもないと焼き込み/覆い焼きした部分とそうでない部分の境界線がはっきり出てしまってみっともない。また、具体的に何秒減らし、増しということは一概には言えないのでケースバイケースで対応することになる。多階調の印画紙を使っている場含には、焼き込む際に号数のより低いフィルターに替えるとより白い部分のディテールが出やすくなるので便利である。とにかく印画紙の真っ白や真っ黒な部分は敵と思って号数のセレクト・焼き込み/覆い焼きをするべきだ。
ネガをいくら綺麗にしたつもりでも、プリント上に白い斑点や糸屑が出てしまうのは良くある話だ。それを修正することをスポッティングと言う。専用の筆と絵の具が市販されているので、特に展示用の写真に対しては必ず行わねばならない。
スポッティングと呼ぶくらいなのでまさに点を、写真の粒子と同じサイズになるくらいの気持ちで筆を立てて埋めてゆくのだ。ここで注意しなければならないのは決して筆を寝かせたり、線を引いたりしないことだ。しばしば忍耐力不足のせいかヤケになって線を引いてしまったり、しまいにはマジックでスポッティングしたりする人がいるが、世が世なら斬り捨てられても文句は言えまい。真のスポッティングの達人は墨汁のみで芸術的な作品を物にする。大切なのは一生懸命スポッティングカラーの色を合わせることなのではなく点の密度で濃淡を表現することなのだと教えてくれる。なんと、カラープリントにも墨汁しか使わない猛者もいるのだ。テクではなく、忍耐力だよ、スポッティングは。
その存在感ある質感のために現在でもプロを中心に愛用され続けているバライタ印画紙。皆さんもパネル貼りの時に使うかと思うので、注意すべき点だけを簡単に述べたい。
先にも述べたが、バラィタはその特性上、水洗時間が非常に長くかかる。RCタイプが5〜10分で済むところをバライタでは60〜90分かかる。このへんを知らない人が案外多く、バライタなのにサッと水洗から揚げてしまって後日変色の憂き目にあっているのだ。
この水洗を完全なものにする為、また時間を短縮するためにはフィルム現像のときに使う水洗促進剤をつかうとよい。これを使うと、(薄手印画紙の場合)予洗1分→水洗促進浴2分→水洗10分のトータル13分で完全な水洗が出来る。詳しくは富士QWの袋に書いてあるので参照のこと。さて、だいぶ書いてきた。ではそろそろお別れを、といきたいところだが最後にフィルムの現像データを紹介して締めたい。
|
|
|
|
|
|
| SPD(1:1) |
|
|
|
|
| フジドール |
|
|
|
|
| ミクロファイン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD(1:1) |
|
|
|
|
| フジドール |
|
|
|
|
| フジドール(1:1) |
|
|
|
|
| ミクロファイン |
|
|
|
|
| ミクロファイン(1:1) |
|
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD(1:1) |
|
|
|
|
| フジドール |
|
|
|
|
| フジドール(1:1) |
|
|
|
|
| ミクロファイン |
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
|
| D−76(1:1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD(1:1) |
|
|
|
|
| フジドール |
|
|
|
|
| フジドール(1:1) |
|
|
|
|
| ミクロファイン |
|
|
|
|
| ミクロファイン(1:1) |
|
|
|
|
| D−76(1:1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD |
|
|
|
|
| SPD(1:1) |
|
|
|
|
| フジドール |
|
|
|
|
| フジドール(1:1) |
|
|
|
|
| ミクロファイン |
|
|
|
|
| ミクロファイン(1:1) |
|
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
|
注:EIとはExposure Indexの略で、実際に撮影や現像をした結果の感度という意味である。現像液や現像時間によって実際の感度は変化するので、撮影時に度の現像液で現像するか考えて、その感度をカメラや露出計にセットすること。また、(1:1)とは現像液1部に水1部を加えて希釈する場合を示している。この場合、若干粒状性は低下するが、シャープネスが高まり、コントラストの低いネガが出来る。
|
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
| T−MAX RS |
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
| HC−110(B希釈) |
|
|
|
| マイクロドールX |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
| T−MAX RS |
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
| HC−110(B希釈) |
|
|
|
| マイクロドールX |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
| T−MAX RS |
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
| D−76(1:1) |
|
|
|
| HC−110(B希釈) |
|
|
|
| マイクロドールX(EI=>50) |
|
|
|
| マイクロドールX(1:1)(EI=>100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
| T−MAX RS |
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
| D−76(1:1) |
|
|
|
| HC−110(B希釈) |
|
|
|
| マイクロドールX(EI=>400) |
|
|
|
| マイクロドールX(1:1)(EI=>400) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
|
| T−MAX |
|
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
|
| D−76 |
|
|
|
|
注:コダック社指定の現像時間では、一般的な引伸し機に対してコントラストが上がりすぎる傾向がある。これは同社のデータが散光式引伸し機を基準に設定されているためで、集散光式引伸し機を使う場合には現像時間を80%程度に抑えたほうがプリントしやすい。
インターネット版の注:イルフォード社のフィルムに対しては手持ちのデータが不十分なため掲載を見送った。今後の研究課題として真摯に対応させていただく。