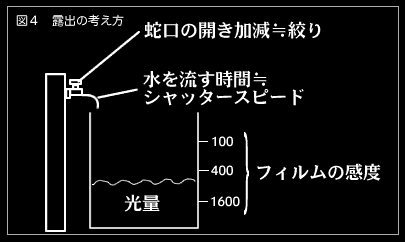
カメラ、レンズ、フィルムがカメラの三要素であった。カメラ、レンズと述べてきていよいよ三要素の最後、フィルムの話になった。今でこそ当然のように缶に入っているフィルムだが、世界初のフィルムは何とアスファルトの板だった。アスファルトが光によって固まる性質を利用してその板をカメラに入れ、風景などを1日がかり、約8時間かけて露光したのだ。そして露光後、その板をラベンダーオイルで洗うと固くなった部分だけが残り、いわゆるネガ像を作ることができたのだ。この手法はキリシャ語の「太陽」と「描く」という言葉を合成して「ヘリオグラフィー」と呼ばれている。1826年頃、フランスのニエプス(Joseph Nicephore Niepce、1765〜1833)が発明したのである。しかし、それでは余りにも撮影に時間がかかり過ぎるというので次には銀板に沃化物を化合させ、それで撮影して水銀蒸気で現像する方法が考え出された。これを発明したのはこれまたフランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(Louis Jacques Mande Daguerre,1781〜1851)であり、この手法は彼の名前にちなんで「ダゲレオタイプ」と呼ばれることになった。これが公にされたのは1839年8月9日のことである。
これによって大幅に撮影時間が短縮され、人物の写真が多く残されることとなったが、しかし、この方法も銀板を利用しているために複製、すなわち現代の写真のように一枚のネガから何枚も焼き増すことが出来ないため、これに対しては銀板の代わりに紙をベースにすることが考案された。これは紙に塩化銀を染み込ませたものを感光紙として作り、撮影してから塩化ナトリウムで現像し、臭化カリウムで定着して紙ネガを作る。これを先の塩化銀紙と密着させて処理すれば黒白プリントの出来上がりというわけだ。この方法では同じネガから何枚ものプリントが作成出来たので、世界初の写真集を生み出すきっかけとなった。この手法はイギリスのウイリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(William Henry Fox Talbot,1800〜1877)によってほぼダゲレオタイプと同時期に発明され、カロタイプあるいはタルボタイプと呼ばれている。一説によればこちらの方がダゲレオタイプより先に発明されていたのだが、発表が遅れたためにダゲレオタイプが世界最初の写真として認知されるようになってしまい、タルボットは大変なショックを受けたといわれている。
しかしこのカロタイプは複製できて使利だがいかんせん紙の繊維のためにシャープさに欠けていた。ならダゲレオタイプでOKかといっても画質は良いが写真は完全な一点物になってしまう。けれども科学の進歩とは凄いものでこの間題に対してはガラス板をベースにする方法が考えられた。ここまでくるといよいよ現代のフィルムに近づいた印象があるが、この方法も初期には感度が低く、しかも撮影する直前に感光材料を塗って乾かないうちに撮影・現像をせねばならないという実に不便なものであった。この手法は湿板写真と呼ばれ、1851年にイギリスのフレデリック・スコット・アーチャーによって発明されている。それではそれを乾いたまま使えるようにすれば良いではないか、というのは当然の話で、この方式もやがて乾板(同じガラスを使うが、乾いたものが市販されるようになった)の発明によって廃れ、そのペースもガラスからセルロイド、そして現代ではTAC(Tri Acetate Cellulose)に替わるに至ると同時に感度の上昇・微粒子化・そしてカラー化が図られて現代に至っているのである。
何となくフィルムの歴史を概観してみたが、いかがであろうか。日頃何気無く撮っている写真も実はこれらの先人たちの努力によって創り上げられたことに感慨を覚えないだろうか,しかしそんな事を知ったからといって良い写真が撮れるだろうか。否。それでは本題に入りたい。
一口にフィルムと行っても様々な分類がある。
1・カラーネガティヴフィルム
いわゆる普通のフィルムで、現像するとカラーのネガ像が出来、それをカラー印画紙にプリントして観賞するもの。
2・カラーリバーサルフィルム
スライド作成用あるいは印刷原稿用に使われるフィルムで、現像すると直ちにカラーのポジ像が出来上がる。カラーネガティブフィルムのようにプリント段階での色補正・露出補正が利かないためその分撮影はシビアになるが、撮影時の意図がもろに反映するためプロや上級アマチュアに愛用者が多い。
3・黒白フィルム
黒白プリントを得るためのフィルム。黒白のネガ像を黒白印画紙にプリントして観賞する。本稿は特に高校写真部向けに書いているので、ここでは特に黒白フィルムについて解説したい。ところで先程から「白黒」ではなく「黒白」と書いているのだが、これは英語のBlack&Whiteの訳語であり、専門書、文献にも「黒白」の表記が使われているので、ここでもそれに倣うことにしたい。最初は慣れなくて違和感があるかもしれないが、どうかお付き含い願いたい。さて、その黒白フィルムであるが、一日にフィルムフィルムと云ってもまた枝葉のように様々なサイズや感度のものが用意されている。ISO(感度の単位。昔はASAといい、当時のカメラにもASAの表示があるが、ISOと全く同様に扱って差し支えない)感度としての種類は25〜3200まで各種、サイズとしての種類はミノックス判(8×12ミリ)から8x
10”(インチ、通称バイテン)とあり、これらを組み含わせるとフィルムの晶種は多岐にわたっている。だが、初めは皆135サイズのフィルムから入ると思うので、その話をしたい。
ところで、「感度」とは何であろうか。テレピでデーモン小暮や高鳴ファミリーが「スーパーGACE400!」などと叫んでいるが、その「400」という数字がフィルムの感度なのである。カメラ店に行ってフィルムを選ぷとき、ナントカ100はナニナニ400より安いからいいね、などと思わず言ってしまうアレである。何となく察しがつくと思うが、ナントカ100よりナニナニ400の方が感度は高い。某400フィルムのパッケージに「ピントに強く、色に強い」などと書かれているのを見ると、やっぱり感度400の方が高いし、こちらのほうが高級なフィルムなのかな、と惑わされがちだが、それは違う。
写真が写るためには光が必要だ。そしてカメラはフィルムに当てる光の量を制御するためにシャッターと絞りを持っている。シャッターはレンズの開日する時間を使ってその働きをし、絞りはそのレンズ径を調節して同じことをするのである。露出の説明にしばしば水と蛇口の関係が使われる。(下図)
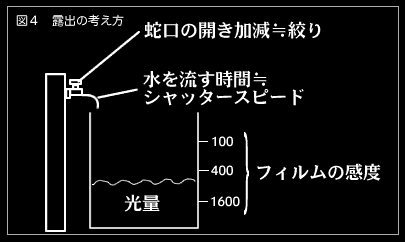
上の図の蛇口の下においてあるバケツ(?)の目盛りに光の量を合わせて入れないとそのフィルムに適した光の量にならず、露出工ラーになってしまう。図で分かるように、感度の高いフィルムほど少ない光の量で写すことができるのだ。即ち、速いシャッタースピード、より絞り込んだ絞りで撮影できるということである。勿論、絶対的なその場の光の量が少ない場合にも有利で、室内や夕景の撮影にも適しているのだ。
しかし、その感度と画質は相反してしまうのだ、残念な事に。写真が銀の粒子で出来ていることは何度も述べたが、高感度なフィルムになればなるほど光を多く取り入れるために一粒一粒の銀の粒子を大きく作らなければならないので写真は粗くなってしまうのだ。カラーフィルムについてもこれは同様で、一概にl
00より400のほうが良いフィルムだとは言えない理由がここにある。先に述ぺた「ピントに強く一」という意味も今や明白だろう。感度が高い→絞り込める→被写界深度が深くなる→ピントが合いやすくなるというカラクリなのだ。ピントに強くなっても、厳密には100や50のフィルムでしっかり撮ったほうが画質は良いのである。(三脚などを使って遅くなるシャッタースピードに対応すること)勿論、400や1600のフィルムが便利な場合も多いのでどんどん使いたい。
さてその絞りとシャッターの話に移ろう。カメラのレンズや液晶パネルにやれ2.8だの125だの、一体コレ何よ?と思っている皆さんも密かにいることだろう。これからその話をしよう。
まず絞り。カメラのレンズに刻んであったり、液晶に出たりする数字に4や5.6や8などがあるが、これを「紋り値」という。数字が大きくなるほど絞り込まれている(絞りの径が小さくなっている→光が入りにくくなっている)状態を示す。そのレンズの絞りを最小の数値にした状態を「絞り開放」と言うのだが、この開放の値が小さければ小さいほど暗い所に強く、また大きなボケを使えることは先に述べた通り。そうしたレンズのはうが使いやすいのだが、大きく、重く、高い。その点単焦点の50ミリレンズの多くはF1.8〜1.2の大口径を持ち、(大口径の正確な定義はないが、概ねF2以下のレンズはそう呼ばれる)しかも2〜3万円くらいで買えるので是非!というか嫁さんを質に入れてでも持って欲しいレンズである。4、5.6などの数字はFナンバーとも呼ばれ、その方が一般的である。「えふよん」「えふごうてんろく」と読む。
そしてシャッター篇。1000とか250という数字でカメラには表示されているが、正確にはこれは逆数であり、実際にはl/1000秒や1/250秒なのだ。もちろん1/250より1/1000の方が早いシャッタースピードなのは言うまでもない。高速シャッターによる勤きの凍結や低速シャッターによる動きの表現が可能になるが、余り遅いシャッタースピードになるとブレやすいので注意。
また、Bという文字も表示されるが、これは「バルブ」と読み、このモードにするとシャッ夕ーボタンを押している間じゅうシャッターが開き続ける。天体写真などに使うモードだ。絞りにもシャッタースピードにも表示の順番というか、決まりというか、万国共通のステップがあるので、それを表にしてみる。頭の柔らかい皆さんにはすぐにお分かりかと思うが、シャッターを遅くすれぱ絞りを絞ることが出来、絞りを開ければ必然的にシャッターは早くせざるを得ない。つまりここでは絶対に絞りを絞りたい、そして同時に高速シャッターを切りたい一というワガママは許されないのだ。ある一定の明るさに対するシャッターと絞りの組み合わせは限られるものなのだ。
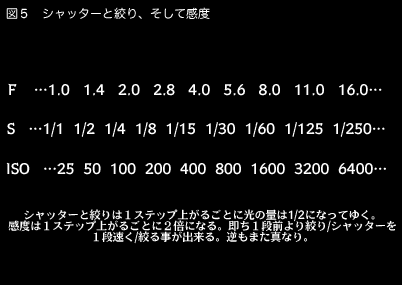
これは大事なことなのだが、絞りもシャッタースピードも1ステップ上がるごとに(F4⇒F5.6・1/15⇒1/30のように)光の量は1/2になっていく。F4はF5.6の倍の光量、1/250秒はl/500秒の倍の光量というように。そして、感度の数植は1ステップ上がるごとに絞り・またはシャッ夕ースピードのいずれか一方を一段上げることが出来る。少し難しいかと思うが、慣れるまでの辛抱だ。この関係が分かるようになると、被写界深度や動感のコントロールが自由にできるようになり、表現に幅が生まれることと思う。まあ最初は、日中⇒ISO100、室内・薄暮・量天・スポーツ⇒ISO400、夜間室内⇒ISO1600を使うのだ、と覚えておけぱよい。さて、話題を少し変えよう。最近のカメラは実に多機能化が進んでおり、「露出モード」にも様々なものがみられるようになった。カメラのカタログや説明書には「絞り優先オート」「シャッタースピード優先オート」「プログラムオート」など、初めて見る人には何が何だか分からない用語が並んでいる。ここではそれの説明を。
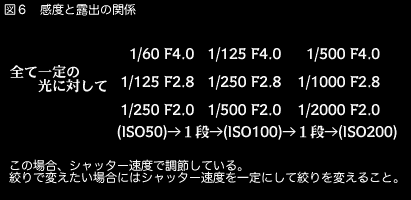
ある一定の光にに対して求められる露出は限られているのは先に述ぺたとおりだが、そのうち被りを任意に決め、シャッタースピードをカメうに任せるのが「紋り優先」、またシャッタースピードを任意に決めて織りをカメうに決めさせるのが「シャッター優先」、シャッターも絞りもカメラに任せてしまうのが「プログラムオート」なのだ。まあ始めはプログラムで(古いカメラには残念ながら付いていない)撮ってよいと思う。慣れてきて、絞りやシャッターの効果をコントロールしたいとなったらそれぞれのモードに切り替えればよいのである。
因みに、大体どのくらいの絞りを普段使えばよいのかということであるが、レンズの性能が最も良く発揮される絞り値はその開放値から2〜3ステップ絞ったところであるので、それを参考にして欲しい。まあそれでも被写界深度が物足りないことが多いので屋外撮影ではF5.6〜11までは絞ってもよいだろう。また、カメラには「露出補正」という機能もある。何故、露出をわざわざ補正しなければならないのだろうか。
それは、実はカメラは実はだまされやすいからなのだ。普段、我々が物を見ているときに何が明るくて何が暗いと評価する基準はその物休の反射率である。白いものが明るく(反射率大)、黒いものは黒く(反射率小)見えるのは、光源の光をその物体がどれだけ反射するかにかかっているのだ。それと同様に、カメラは内部にセンサーをもっており、それで周囲の反射の明るさを測っている。そこで露出が決められるというわけなのだが、ここに落とし穴があるのだ。誰が発見したか知らないが、世の中の、目に見えるもの全ての反射率を混然一体にしたら18%になるという法則がある。ちょうど道路のアスファルトや、日本人の肌色くらいの反射率だ。実はカメラの露出はこの理論にしたがって設定されているのだが、言い換えるとこれはどんな物でもグレーに(18%グレー、18%の反射率はグレーに見える)持っていくようになっているのである。スキーに行って雪景色を撮ったとき、雪がグレーに写ってしまった経験はないだろうか。あるいは砂浜の景色、白いシャッでもこのような状態に陥る。また、黒い壁や学生服がグレーになってしまうことも多い。このようなときに露出補正を使えば正しく写すことが出来る。白がグレーになる条件に対しては+1/2〜2のオーバー補正、黒がグレーになる条件に対しては-1/2〜11/2のアンダー補正が効果的だ。白いもの、黒いものを画面一杯に写し込んだときにもこの補正を掛けないと、後でシマッタ、ということになる。また、曇り空を大きく取り込んだ構図のときには+1〜2段の補正、逆光でシルエットを撮りたいときには-1段ほどの補正をするとよい。逆もまた真なりで、逆光で人物などの顔を出したいときには+1〜2段の補正をしないときれいに写らない。上に述ぺたことはマニュアル露出時にも同じで、その場合にはカメラの露出の指示値から+の時には絞りを開ける/シャッターを遅くする、-の時には絞りを絞る/シャッターを速くするということをすれぱ良いのだ。
以上、長々と露出の話が続いてきたが、こんな能書きはどうでも良いのだ。まずは、何度も言うように、とにかく撮りまくること。そして多くの失敗を経験すること。その上でもう一度この冊子に目を通していただくとありがたい。最後に各シャッタースピードと絞りの効果について、日本コダックのフィルムガイドに良い表が載っているので引用してこの章の締めくくりとしたい。
|
|
|
|
| 開放 | その場の弱い光だけで撮影するような場合に適しています。被写界深度は最も浅くなり、レンズの性能は最も低くなります。 | F2 |
| 開放より1段絞る | 少ない光量下での撮影に適しています。被写界深度は浅くなりますが、背景をぼかして、被写体だけを引き立たせる効果が出せます。レンズの性能は良好です。 | F2.8 |
| 開放より1〜2段階絞る | 最高のレンズ性能が引き出せます。被写界深度は一層深くなり、ピントの合う範囲も広がります。曇天や日陰など、光量がやや不十分な条件での撮影に向いています。 |
F4 F5.6 |
| 最大絞り込みよりも2段階開ける | 被写界深度は中程度。戸外、昼光での撮影に適しています。高いレンズ性能を引き出せます。 | F8 |
| 最大絞り込みよりも1段階開ける | 被写界深度はさらに深くなり、戸外の昼光での撮影全般に向いています。高いレンズ性能を引き出せます。 | F11 |
| 最大絞り込み | 被写界深度は最も深くなりますが、光学的な作用によって、鮮明度はわずかに低下します。しかし、鮮明度の低下は、殆ど気付かない程度なので、被写界深度の深さを最大限に生かしたいときにはこの絞りが有効です。 | F16 |
|
|
|
| B(バルブ) | シャッターボタンを押している間中、シャッターは開いています。夜の戸外の撮影で、被写界深度を深くしたい場合や花火や稲妻の撮影、または夜の自動車のライトのように光が流れる情景を撮影するのに適しています。長時間露光ではフレアなどが生じることがありますので注意して下さい。三脚でカメラを固定して下さい。 |
| 1秒〜1/2秒 | その場の光やフォトランプのような低光量下で、しかも被写界深度を深くしたい場合の撮影、例えば、静物の撮影に向いています。このシャッタースピードでは、カラーフィルムの場合、わずかにフレアを生じることがあります。三脚でカメラを固定して下さい。 |
| 1/4秒 | 大人のポートレート撮影に使える最も遅いシャッター速度です。低光量下で、レンズを絞り込んで被写界深度を深くしたい場合や静物の撮影に適しています。カメラを三脚に固定して下さい。 |
| 1/8秒 | 近距離での大人のポートレート撮影には1/4秒より1/8秒の方が適しています。低光量下で被写界深度を深くしたい場合や、静物の撮影に適しています。カメラを三脚に固定して下さい。 |
| 1/15秒 | 標準レンズや広角レンズを使っている場合であれば、人によっては手持ちでも撮影可能です。その場合にはカメラをしっかりと持って下さい。一般的にはその場の光などの低光量下でレンズを絞り込んで被写界深度を深くしたい場合の撮影に適しています。カメラを三脚に固定して下さい。 |
| 1/30秒 | 標準レンズや広角レンズで、手持ちで撮影できる最も遅いシャッター速度です。カメラをしっかり持たないと、カメラブレを起こします。このシャッター速度は、その場の光での撮影全般に使えます。また曇天や日陰で、レンズを絞り込んで被写界深度を深くしたい場合の撮影に適しています。殆どのカメラでフラッシュバルブを使う場合やレンジファインダーの付いたカメラでストロボを使う場合には、このシャッター速度※をお奨めします。 |
| 1/60秒 | 昼間の戸外の撮影で、光量がやや不足の場合、たとえば曇天、日陰、逆光等の場合に適しています。被写界深度を深くしたい場合にも使いやすいシャッター速度です。1/30秒よりも、カメラブレによる失敗は少なくなります。多くの一眼レフカメラの場合、ストロボ撮影にはこのシャッター速度※を使います。 |
| 1/125秒 | 昼間の戸外の撮影全般に最適のシャッター速度です。光量が十分な場合には、比較的レンズを絞って被写界深度が得られますし、わずかにカメラがブレても画像には殆ど影響がありません。また、歩いている人、遊んでいる子ども、動き回っている赤ん坊などの穏やかな動きなら、ほぼ画像を止められます。このシャッター速度は、焦点距離が105ミリもしくはそれよりも短い望遠レンズで手持ち撮影できる最も遅い速度です。またストロボ撮影にこのシャッター速度※をすすめている一眼レフカメラもあります。 |
| 1/250秒 | 中程度の早さの動きを止めるのに適しています。ランニング、水泳、ゆっくり走っている自転車、遠くで走る馬、パレード、走っている子ども、ヨット、それほど素早く動いていない野球やフットボールの選手などです。特に太陽光下での撮影で被写界深度を深くする必要がなく、何かの動きを停止させて撮影したい場合に適し、カメラブレをなくすのにも役立ちます。焦点距離250ミリまでの望遠レンズの手持ち撮影に適しています。 |
| 1/500秒 | 速い動きを停止させるのに適しています。例えば、速く走っている人、少し遠くの方で走っている馬、速い自転車、走っている車、バスケットボールの選手などです。特別に速い動き以外は、ほとんどすべての動きを止めるのに使えるシャッター速度です。また、1/1000秒を使うよりも被写界深度を深く出来ます。望遠レンズでの撮影に最適のシャッター速度で、焦点距離400ミリまでのレンズでの手持ち撮影に適しています。 |
| 1/1000秒 | 自動車レース、オートバイ、飛行機、ボートレース、陸上競技、テニス、スキー、ゴルフなど、特に速い動きを止めるのに最適です。このシャッター速度では、レンズをあまり絞り込めないので、被写界深度は浅くなります。焦点距離の長い望遠レンズの手持ち撮影に絶好のシャッター速度です。 |
| 1/2000秒 | モータースポーツ、テニスラケットのスゥイングなど、目にも止まらない速い動きを確認するのに最適です。レンズの絞りを大きく開ける必要があり、被写界深度も極めて浅くなります。また、焦点距離の長い望遠レンズの手持ち撮影に絶好のシャッター速度です。 |
※ストロボ撮影などのフラッシュ撮影時の適切なシャッター速度については、カメラの説明書をよくお読み下さい。