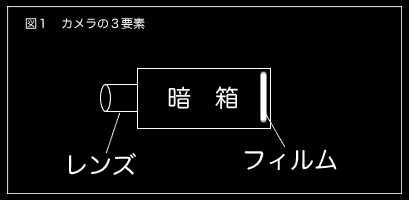
カメラは今や全くありふれた道具になった。80年代に富士フィルムから発売された写ルンです(レンズ付きカメラ)は、当初全く流行らないだろう、という周囲の予想を見事に裏切って、今や全フィルム出荷量の3割を占めるようになった。皆さんも使ったことがあると思うが、あれで本当に「写ル」のだから恐れ人る。しかしあのような商品が作られ.実用出来るようになった陰にはフィルムの発連が寄与しているのだ。どうしてか、については後で書くことにしよう。さて、そのカメラにも様々な形をしたものがある。写ルンですからズーム付きコンパクトカメラ、ズーム出来ないコンパクトカメラ、やたら値段が高いコンパクトカメラ、入門機から高級機まで揃った一眼レフカメラ、蛇腹のついた大型カメラなどなど。皆一緒じゃないか、と思われるだろう。そう、本当に一緒なのである。カメラがカメラたる条件は3つある。すなわち・レンズ・フィルム・暗箱の3要素である。先にあげたどんなカメラにもこの3つの要素は含まれていて、違うように見えるのは単に用途に応じてそれぞれ進化していったからなのだ。
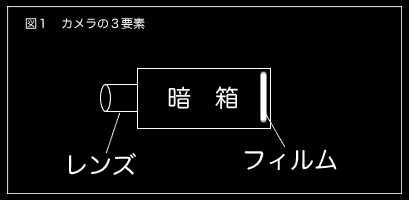
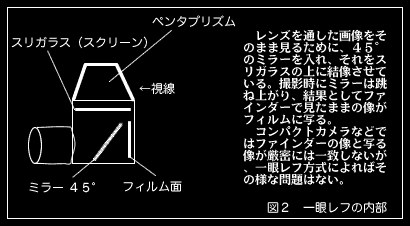
とにかく、上の三要素が揃えばとりあえずカメラの形になり、写真は写るのだ。ではそれぞれのカメラの特徴と用途について簡単に述べたい。
(1)コンパクトカメラ
家庭の記念写真が撮れれぱよい、というだけではなく、最近では高級嗜好の品(コンタックスT2、ミノルタTC一l、ニコン35/28Ti、コニカヘキサー等)も流行している。一般のコンパクトとの違いと言えばまずレンズへのこだわりがみられる。一眼レフカメラ用レンズ並み、あるいはそれ以上の画質を目指して手抜きのないレンズ構成は全紙大に引き伸ばしても破綻のない画質を見せてくれるし、大口径レンズ(後述)の採用で暗い場所や高速シャッター(後述)にも余裕で対応できる。よって、プロカメラマンにも愛用者は多い。しかしそうした高級機はともかく、一般的には「分かり易く、使いやすく」をモットーに作られているため即写性やコンパクト性には優れているものの、これから写真を本格的に始めようという皆さんには向かないであろう。
この種のカメラはレンズ交換ができず、マニュアル操作で写真に手心を加えることもできないのである。「いつもカメラを持ち歩け」というポリシーに応えるために敢えてお薦めするならばオリンパスミューやコニカビッグミニ、予算が許すならコンタックスT2などだろうか。ズームなど要らないし、なるべく小さいものが欲しいとなるとこの選択に落ち着くのだ。近頃ではどんな電気製品も多機能化が進み、カメラもその例に漏れない。やたらと小さなボタンがプチプチと並ぷ機種は後で混乱するのだ。でも、俺自身はコンパクトカメラで撮られた写真を否定する気もないし、コンパクトカメラで撮った写真だけで写真集が出る時代なのだ。だだ何故薦めないのかと言えば、写真の基礎−ピント合わせや露出の何たるかが学べないからなのだ。それらを覚えて初めてコンパクトカメラの長所短所が分かり、思い通りに使いこなせるようになるのだ。だからまず一眼レフカメラを使ってみて欲しい。それから持つコンパクトカメラにこそ意義があり、良い作品を生み出す道具になるのだ。
(2)一眼レフカメラ
現在手に入れることの出来るカメラでこれ程発展的なカメラは他にない。豊富な交換レンズ群、意のままにシャッターと絞り(この組み合わせを露出という)を操れ、明るいファインダーで見たままの絵を写真にできる一コンパクトカメラにも自分でマニュアル操作が可能なものもあるが、結局それも付加的なものに過ぎず、やはり写真を「作る」「学ぷ」という点では一眼レフカメラに止めをさす。一眼レフカメラにも弱点はあって、まず大きく重い。一眼レフカメラはミラーを内蔵しなけれぱならない関係上、そのスペースのために小型化は犠牲になる。またこれもミラーの宿命で写っている瞬間はファインダーで確認できない。何しろ1つのレンズでファインダーと撮影の2つの役目を持だせているのだから諦めるほかない。(ミラーを半透明にしてこれを克服したカメラもある。[キャノンEOS-1nRS、ニコンF3H{受注生産品}])そしてこれまたミラーの都合でレンズが大型化してしまう。一眼レフカメラの欠点も長所もつまるところこのミラーに負っている。しかしミラーの短所をかくも並ぺ上げ、あだかもミラーが悪者かのように書いだが、ミラーが入っていなけれぱ実現できないことが一つある。それは「見たままを写す」ということである。皆さんご存じのコンパクトカメラを見ていて気付き、まだ不思議に思うことはないだろうか。「何故ファインダーとレンズが離れていても狙ったところが撮れるのだろう一」そこである。厳密に言うと、その種のカメラでは狙った通りの絵柄は写っていないのである。冷静に考えるとそれは当然であり、また不気味ではないだろうか。思ったところが写っていない一一眼レフカメラが普及する以前の写真家はこの事実との戦いの日々を繰り広げていたのだった。しかし意外なことに一眼レフカメラの発想は18世紀以前からあり、感光材料、即ち銀板やアスファルトが発明される以前はカメラとは写真を撮る道具ではなく、そのピント面に薄紙を置いて風景を模写するための画家の道具だったのだが、その道具一カメラ・オブスキュラは簡単ながらもレンズを持ち、ミラーを持ち、フィルムさえ発明されていればそのままカメラに成り得るものであった。そうした機構自体は知られていだのに、何故最初のカメラから一眼レフにならなかっだのかと言えば、やはり作るのが難しかったからであろうとしか言えない。
現代において最もボピュラーないわゆるコンビニでも買えるフィルム(135サイズ)を用いる一眼レフカメラの最初はドイツのツァイス・イコン社から発売されたペンタブリズム付きのコンタックスSである。数年前に京セラがコンタックスS2をこのカメラに因んで「カメラ・ルネッサンス」というコピーとともに売り出しだのは記憶に新しいところだ。ちなみに初めて135サイズのフィルムを使ったカメラは言わずと知れたライカである。
さて長々と話をしてしまったが、これから一眼レフカメラを選ぼうとする皆さんにとって、コンタックスSにしてみれぱ大変贅沢な悩みがある。それはAF(オートフォーカス)にするかMF(マニュアルフォーカス)にするかという事である。AF機とは例えばミノルタのα507si、キャノンEOS55、ニコンF90などの様に、レンズの駆動機構を持ちほとんど全自動で撮れるカメラであり、MF機と言えばミノルタX700、ニコンFM2、コンタックスRXなどの様に、ピント合わせを手動で行わねぱならない種類のカメラである。AFは素人臭い、でもピント合わせが不安な俺にはいいかもと思ったり、MF機はプロっぼいけど古臭いし一などと様々な悩みがあると思う。しかし俺は初心者の皆さんにはAFの全自動で本数をこなし、写真に味付けをしてみたいと思うようになったらオート機能を解除したり、思い切ってMFの渋いカメラを買ったりするのがいいと思う。金のない諸兄には中古カメラもお薦めだ。新宿や銀座には中古カメラ店がたくさんあるので、カメラ雑誌でチェックされたい。さてお薦めのカメラという話になると独断と偏見、趣味の世界になるので一応書いておくが聞き流していただきたい。
挙げてゆけばきりのないカメラフェチ若林なのだが、一応買いやすい予算で使いやすいカメラを挙げてみたつもりだ。よってEOS-1nやF4などのいわゆる高いカメラは挙げられていないのだが、これらは最初に使うカメラとしては必要にして十分なカメラばかりである。また、「新品」としてあげられているカメラの中古品も出回っているので、そちらも検討されたい。カメラに詳しい人と買いにいくのが安心なのはいうまでもない。筆者若林で良ければいつでも参上するので連絡乞う。というわけで、まずはAF、オートで撮りまくれと言ってこの項の綿めくくりとしたい。
(3)中型カメラ
コンビニで買えるあのフィルムは、実は正式には135サイズ、35ミリ判という。24×35ミリの面積を持つネガやボジを写すのでそう呼ぷのである。何故36ミリなのに35ミリ版と呼ぷのかは俺も知らない。ご存じの方もあるだろうが、実はフィルムには様々なサイズのものがある。スパイカメラに使われる8×11ミリサイズのものからおよそA4版のサイズを持つ8×10インチのフィルムに至るまで、全く様々である。その中に120サイズ、即ち70ミリ幅のロールフィルムがあるのだが、これを使うカメラを総称して中判(中型)カメラと呼ぷのである。フィルムのサイズは大きけれぱ大きいほど画質的には有利になる。例えば135サイズのネガと6×6センチサイズ(ロクロクと呼ぷ)を同じサイズに引き伸ばす場合、前者のネガ面積は864平方ミリメートル、後者のネガ面積は3600平方ミリメートルであり、拡大の倍率は6×6サイズの方が大幅に低いことになる。即ち同じフィルムを使っても粒子やピントのアラが目立だずに済み、高画質が得られるわけだ。ビデオやデジタルカメラのCCDは「画素数」でその善し悪しが言われるが、ちょうどそれと同じ理屈である。面積の大きいフィルムのほうがより多くの銀粒子(≒画素)を含み、それだけ画質がよいということだ。さてその120サイズのフィルムは使用するカメラによって撮影できる枚数が決まってくる。一日に中判カメラで同じフィルムを使うと言っても、様々なサイズと枚数を選ぷことができるのだ。6×4.5(15枚)、6×6(12枚)、6×7(10枚)、6×8(9枚〉、6×9(8枚)などのサイズが主なものとして挙げられる。フィルムの幅は一定なため、すぺて「6×」で始まるのだが、残りの辺の長さには様々なバリエーションがあり、用途や好みによって選ぷことができる。
いい事ずくめにも見える中判カメラではあるが、やはり弱点はあって、まず大きく重い。フィルムが大きいため、シャッターもレンズもボディーも大きくなってしまう。そして値段も大きく重い。月に数百台しか売れないし、多少高くても本当に必要としているプロは買ってしまうので競争の原理、神の見えざる手が働かないのだ。まあ、俺は35ミリは押さえたぜ!という向きには一度使ってもらいたいカメラである。まずは安く買える二眼レフ(テクサー、または中古のローライコードなど)がお薦めだ.その程度のカメラでも驚くほどの高画質が望める。
新品は俺でも買えない程なので中古ばかりを紹介した。基本的に中判カメラは大同小異で、モデルチェンジも5年に一度(もしない)というように、中古を買ったからといってやれこの機能が無いとかここが不便だ(不使さも20年前から変わらない。覚悟して買え!)などという事が無いので、最新型にこだわる必要はない。中判カメラはそれぞれに用途が決まっている、というかこれは静物用、これは風景用というように何となく向き不向きがあるので購入と使用に当ってはその種の本を読むか、詳しい人の指導を受けたほうがよろしかろう。
(4)大型カメラ
中判よりさらに大きい、4×5インチ、5×7インチ、あるいは8×10インチのフィルムを使うカメラの総称である。ここまでフィルムが大きくなるとさすがに巻き取っておけなくなるので1枚1枚にカットされたシートフィルムとなっており、それをフィルムホルダーという枠に入れて使わなければならないので非常に不便である。この種のカメラはほとんどカメラの「原形」をとどめていると言ってよい。
フィルムを支える枠とレンズを支える枠、そしてこの2者を接続する蛇腹一何故今更このようなカメラを使わねぱならないのか。その答えは中判を越えた高画質とカメラ・ムーヴメント(アオリ機構)にある。35ミリや中判ではセンチ単位で語られた画面サイズがここでは一気にインチ単位になる。因みに4×5インチはセンチに換算すると10.2×12.7センチになり、これだけでも画質の良さが分かるであろう。まだ、カメラ・ムーヴメント(以下アオリと呼ぷ)とはその蛇腹ゆえに可能となる大型カメラ特有の機構である。一般的なカメラではフィルム面に対してレンズは中心かつ垂直に来るように決められているが、これはあえてこの位置を崩して特別な効果を得ようとするものである.
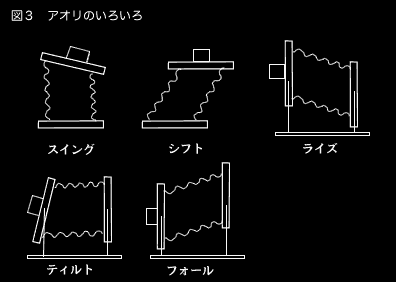
図のうち、ライズ/フォール、シフトにおいてはまだレンズとフィルムは平行なので正しくはアオリとは呼ばないのだが、慣習的にはアオリと呼ばれているのでそれに倣うことにする。アオリの説明は難しく、それだけで1冊出来てしまうかも知れないほどなので簡単に述ぺるが、例えばカメラを地面に向けて足元の雑草から地平線に至るまでを写そうとしたとしよう。一般的なカメラではここで絞りを絞り込んで奥までピントを合わせる方法しか取れないのであるが、そんなときはティルトアオリの出番である。レンズを下向きに振って行くとあら不思議!絞り込まなくても手前から奥にまでピントが合うのである。また、普通のカメラで撮ると上すぼまりになってしまう高層ビルも、ライズを使えばばっちり真っすぐに写すことができる。実は建築写真には絶対に欠かせないのがこの大型カメラなのである。